思えばおそらく、このゲームが人生初のFPSだったのだろう。
そのゲームは、私の周囲でとてつもないブームを巻き起こした。
連日友達の家に集まり、みんなで対戦プレイをしていた。
そしてそれは私の周りだけでは無く、全国の子供たちがそうだったのだろう。
現在でもプレミア価格で中古ソフトが取引されているようだ。
誰もが認める伝説的なソフト。
昔のゲームを思い出すとき、必ず話題に上る名作。
そのゲームは本格的FPSと圧倒的バカゲーの両立に奇跡的に成功した。
手応えのあるシングルプレイに狂気をはらんだ対戦モード。
一人でも、友達とでも。
初心者から上級者まで受け入れる間口の広さ。
そんなゲームをご紹介したい。
さあ、1997年にタイムスリップしよう。
[adchord]
概要
今回ご紹介するのは、一度はタイトルを耳にしたことがあるであろう。
「ゴールデンアイ 007」
である。
発売日 1997年8月23日
発売元 任天堂(開発→レア社)
プラットフォーム NINTENDO64
発売から23年経った現代でも4万円という衝撃的な値段で取引がされている。
それほどに今なお評価されているゲームなのだ。
それと同時に日本にFPSというジャンルを知らしめたともされており、日本ゲーム業界の一つの分岐点だったのではないだろうか。
そんなゲームを、私の想い出と共にご紹介しよう。
制作背景
言わずもがなの人気映画シリーズ、007。
諜報員ジェームズ・ボンドの活躍を描いたこのシリーズの名前は皆さん聞いたことがあるだろう。
「007 ゴールデンアイ」という映画が1995年に公開された。
これがシリーズ17作目である。
それから約2年後にこのゲームが発売されるのだが、確認できる限りでは007シリーズを題材にしたゲームは本作が初だったようだ。
当時は64が発売されてからまだ1年という時期。
家庭用ゲームでFPSが開発されたのには、64に搭載された3Dスティックという機能が大きな影響を与えている。
当然ながら十字キー、方向キーのみではエイムが成り立たない。
そもそもFPSはPCでの操作を前提に発足したジャンルであり、家庭用ゲーム機においての歴史はそう深くない。
厳密に言えばファミコン時代からごく少数発売されてはいたようだが、市場に存在感があったわけではない。
その中でほぼ初に近いほどのセールスを叩き出したのが、このゴールデンアイである。
約800万本という驚異的なセールスを叩き出した本作は、日本のライトゲーム層にFPSというジャンルを認知させたと言えるだろう。
同一の制作チームが同じく64でリリースした「パーフェクトダーク」もまた一定のヒットを記録したが、以降のFPSはXbox360やPS3といった次世代機の流行、それに伴う海外ゲームの移植文化が根付くまで隆盛を待つこととなる。Call Of Dutyシリーズが現れる前と後で環境が大きく変わったのは誰の目から見ても明らかだろう。
つまりはスティックを用いたエイムを導入したFPSというのが当時は斬新かつ画期的だったのである。
[adchord]
緻密に作られたミッション
本作は、映画のシナリオに沿ってステージをクリアしていくミッションモードがメインとなる。
ここで改めて確認するが、これは戦争をモチーフにしたゲームではない。
ジェームズ・ボンドというスパイを主人公としたスパイアクションなのだ。
この点が、本作において重要なのだ。
スパイの基本は潜入だ。
そして的を殲滅することは目的では無く手段だ。
本作のミッションモードにはステージ毎にそれぞれ目的が存在する。
例を挙げていけば
・人質を救出し、脱出。
・装置に爆薬を設置し破壊
・敵の秘密兵器の写真を撮影
・指定された人物の殺害
などがある。
もちろん敵兵だってバカではない、必死に抵抗を試みる。
当時の私は驚いたのが、この敵兵の行動だ。
銃声が聞こえたら周囲から援軍が駆けつける。
またある者は警報器を鳴らそうと駆け出す。
人質を捕らえた敵は迅速に排除しなくては、人質の命が奪われる。
主人公たるジェームズボンドは、基本的に貧相な装備で登場する。
サイレンサー付のハンドガン、ボンドの代名詞、PPKだ。

©MARUZEN
もちろん銃なので敵を倒すこと自体に不自由はしない。
しかし多数を相手にするには、ハンドガンではいささか頼りない。
ならばどうするか。
気付かれないようにこっそり殺害するしかない。
一度敵を倒してしまえば、武器は拾うことが出来る。
そこからは自由だ。
ランボーのごとく蹂躙しても良い。
スパイらしく最小限の撃破に留めるもまた良し。
警報器をまず壊して退路を塞ぐも良し。
またステージによっては敵の装備にスナイパーライフルがあり、見張り台から監視していることもある。
逆に言えば敵兵の距離が遠いため、各個撃破出来れば無問題だったりするわけだ。
これらのステージ構成を見抜き、最適解を出していく作業はメタルギアソリッドにも似た、パズルのような感覚を覚える。
更にはスパイならでは、というかボンドならではのガジェットもしっかり登場してくる。
腕時計に仕込まれたレーザー光線。
スマブラでお馴染み、センサー爆弾。
そして前述したカメラ。
これらを用いて、一人称視点でミッションをクリアするのはまさしく追体験だ。
列車のブレーキユニットを銃で破壊し、床をレーザー光線で打ち抜いて脱出する経験はそうそう日常に訪れない。
没入感というFPSの特徴を最大限活かした、良質なミッションの数々は手応え抜群だ。
また難易度も3種類用意され、最高難易度は鬼畜と呼べる修羅の道となっている。
初心者からやり込み勢まで、長く付き合えるのがミッションモードなのだ。
また他の007シリーズを題材とした隠しステージもあり、それらの難易度は更に別格。
最初から最後まで骨太な設計となっている。
カオスなお楽しみモード
そして規定難易度、規定タイムでのクリアを達成する毎に隠しモードが解放されていく。
こちらはまさしくカオスな様相を呈したお楽しみモードである。
開発であるレア社が制作したドンキーコングシリーズを元とした、顔が極端に巨大化するDKモードや弾痕がカラフルになるペイントモード。
あるいは重力を強めたり弱めたり、敵から視認されなくなったり全員ロケラン持ったり。
こちらの武器も自由に選べるようになり、到底スパイとは思えない機関銃の連射による強行突破など多彩な遊び方が出来る。

引用元・・・http://www.pughoofgaming.com/videos/goldeneye-007s-dk-mode-best-cheats-videogames/
敵も味方も好きにカスタマイズ出来るこのモードは、ご褒美として最適だ。
クリアするのに何度も苦しめられた敵を、あの手この手でけちょんけちょんにして脳みそハッピーになれるのだぞ。
楽しくないわけがない。
最大のヒットの理由、対戦
ここまでシングルプレイの素晴らしさをお伝えしてきた。
しかし、だ。
このゲームをプレイした人の記憶に焼き付いているのは、間違いなく対戦モードだろう。
このゲーム、最大4人で対戦することが出来る。
それも歴代の007をテーマにした風変わりなルールが多数存在している上に、キャラクターも豊富だ。
私も友人宅で何日も何時間も笑い転げながらプレイした記憶がある。
そう、このゲームはパーティゲームとしても優れていたのだ。
今のオンライン対戦が家庭用ゲームでも主流となった時代には考えられないが、このゲームは画面分割による対戦だ。
そのため相手がマップのどの位置に居るか、すぐに把握できてしまう。
これではFPSとして成り立たないでは無いか、と思う人も居るだろう。
ところがどっこい、これがそうでもないんだ。
このゲーム、いくら当時優れた操作性を持っていたとはいえ精密なエイムをするためには棒立ちになって慎重に狙う必要があった。
FPSではそんな行動が出来る余裕などそうそう無い。
その結果展開されたのは、なんとなくのエイムで銃を乱射しながら走り回る4人組というシュールな画だ。
あるいは相手の位置を把握した上での角待ち。
それでも簡単に倒すことが出来ないし、うかうかしてたら他の相手にやられるわけだからそりゃもう阿鼻叫喚の戦いになる。
それが、当時の子供たちには大受けだったのだ。
またルールの多彩さがそれに拍車をかけていた。
どんな体力でも一撃で葬ることが出来る黄金銃、これをどれだけ長く保有できるかを競う「黄金銃を持つ男」。
フラッグを持った瞬間全員から敵意を向けられる「リビング・デイライツ」。
中でも私の周囲が熱中したのは、全ての武器で一撃死となる特殊ルール。
「消されたライセンス」
このモードが異常に盛り上がった。
なぜ消されたライセンスなのか
先程もいったように、このゲームで勝つには
①棒立ちでがっつりエイムする
②走り回りながら乱射する
というどちらかになる。
どちらにしても強い銃を手に入れた瞬間に場を支配し蹂躙することが出来るようになる。
それが、一撃死が確定した瞬間に様相は一変するのだ。
このゲーム、武器を持たない場合の攻撃はチョップになる。
チョップだ。
手刀だ。
本来はほとんど使う場面のない攻撃だ。
しかし一撃死するのがこのルール。
マシンガンを持つ相手だろうがショットガンだろうが、チョップで対抗できるのだ。
頻繁に優劣が入れ替わり、誰にでも勝利の可能性が出るのがこのモードの最大の魅力だった。
おそらく今の操作性に優れたFPSではこうはいかない。
ゲームとして成立するが安定して当てるのはかなり難しい、そんな操作性と特殊ルールが生んだ奇跡のような盛り上がりだったのかもしれない。
正直、スマブラより遙かにランダム性と笑いに富んだ記憶が強い。
蛇足ではあるが、私の周囲では最強武器はグレネードランチャーであった。
皆様はあの銃について仕様をご存じだろうか。

引用元・・・https://echigokuko.militaryblog.jp/e888129.html
この銃は、弾丸を発射するのではない。
擲弾と呼ばれるものを打ち出す装置だ。
擲弾、簡単に言えば手榴弾と考えて良い。
これを発射するということは、山なりに打てるし壁に跳ね返る。
敵がどこに居るか画面で把握した上で反射させることが出来るのだ。
見えないところからグレネードの擲弾だけが画面に飛んでくる瞬間の恐怖は今でも忘れられない。
それでもその射線を潜り抜け、チョップで倒すことが出来たのもまた事実。
3人が手をブンブン振り回しながらグレネード持ちに特攻する様は、笑わずには見られないだろう。
プレイできない名作
このゲームは一応、Wiiにてリメイクされているが、私はプレイしていない。
おそらくだが、あの操作性とグラフィックだから楽しめたのだと思っている。
優秀なリメイクだとしても、それは最早別のゲームなのだ。
だからこそ、文章に残すしか出来ない。
この希代の名作にして伝説となったゲーム。
もし運良くプレイできる機会が訪れたら。
細かいことを気にせず楽しんで頂きたい。
ある意味ノスタルジーに閉じ込めておきたい、そんな作品だ。
想い出ゲームレビューの一覧はこちらからどうぞ。


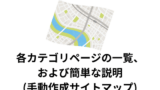

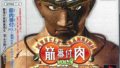
コメント